2025/04/23『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』第3話、見ました。Eテレで『チ。』と『夜廻り猫』やったあとという時間はありがたい。でも、『らんま1/2』と『中禅寺先生』が裏になるのは残念でございます。第3話はマチュとシュウジがマブとなって飛び道具を持った相手にそれ無しで勝つという内容。1stのキャラは脇を支える程度の登場で、これが正解ですよね。望む人もいるだろうけれど、シャアとかアムロとかテムとかも、深く物語に関わらないで欲しいものでございます。独立した物語でございますから。まぁ、アムロラスボスで、鋼鉄ジーグみたいな手足がバンバン飛び出すジーグオングとかに乗って登場し、ジークアクスを圧倒するというのも見てみたくはございますが。
2025/01/03 『仮面ライダー×スーパー戦隊 スーパーヒーロー大戦』を見ました。
YouTubeで13日まで。
仮面ライダーとスーパー戦隊は相容れる存在ではないと、
ゴーカイレッドが大ザンギャックの大帝王を名乗りライダー殲滅を実行、
それに対して、仮面ライダーディケイドは大ショッカーの大首領を名乗り
スーパー戦隊撃滅を目指すという、
戦闘に次ぐ戦闘、それを見せるための作品でございますな。
YouTubeで13日まで。
仮面ライダーとスーパー戦隊は相容れる存在ではないと、
ゴーカイレッドが大ザンギャックの大帝王を名乗りライダー殲滅を実行、
それに対して、仮面ライダーディケイドは大ショッカーの大首領を名乗り
スーパー戦隊撃滅を目指すという、
戦闘に次ぐ戦闘、それを見せるための作品でございますな。
PR
なぞのまとめ 2024/12/15 に書いた
ゴジラのプラモデル、出来上がりました。
ゴジラのプラモデル、出来上がりました。
まぁ、素組みでございますが。
何もしなくてもキチンとはまって、
文句の付けようのない造形になるのはよろしゅうございますな。
手塚プロダクション公式チャンネル。
2025/1/24 14時までの期間限定で映画『ユニコ』が配信されております。
2025/1/24 14時までの期間限定で映画『ユニコ』が配信されております。
ついで12月25日からは『ユニコ 魔法の島へ』が──。
『ユニコ』の方は、原作の
黒猫の女の子・チャオの話と悪魔の子供の話を
アレンジして構成した作品。
黒猫の女の子・チャオの話と悪魔の子供の話を
アレンジして構成した作品。
『ユニコ 魔法の島へ』は、以前紹介いたしましたな。
孤独属性がある方で子供むけでも問題ないという方にはおすすめ。
刺さるものがあると思います。
そうでない方で、宇宙世紀ガンダムが好きな方でございましたら、
池田秀一さんがトルビーの声を当てておられますので、
その演技を確かめるというのも一驚かと思います。
池田秀一さんがトルビーの声を当てておられますので、
その演技を確かめるというのも一驚かと思います。
(上に書こうとして書ききれなくなったのでこちらへ。
アニメ(それも数話抜けてる)を見ただけの感想でございます))
その分ラストは、本当にクリフハンガー。
アニメ(それも数話抜けてる)を見ただけの感想でございます))
『ダンダダン』。
次期が決まっているため、海外ドラマにあるような
クリフハンガー方式で終わりましたな。
物語はラストに近づくまで淡々と進められておりました。
次期が決まっているため、海外ドラマにあるような
クリフハンガー方式で終わりましたな。
物語はラストに近づくまで淡々と進められておりました。
その分ラストは、本当にクリフハンガー。
二期が待ち遠しくございます。
作中の下ネタが話題になったりもしておりましたけれど、
こわいマンガの大家(たいか)
水木しげる先生とか楳図かずお先生も
けっこう下ネタでございますからな。
『ゲゲゲの鬼太郎』ですとか『まことちゃん』ですとか。
こわいマンガの大家(たいか)
水木しげる先生とか楳図かずお先生も
けっこう下ネタでございますからな。
『ゲゲゲの鬼太郎』ですとか『まことちゃん』ですとか。
それにこの作品ではそれらの描き方も、
ずいぶん洗練されたものになっているような気がいたします。
あまり汚さを感じさせないのですな。
(最終話の温泉に登場した大人の男の方々には精神の汚さを感じましてけれど)
ずいぶん洗練されたものになっているような気がいたします。
あまり汚さを感じさせないのですな。
(最終話の温泉に登場した大人の男の方々には精神の汚さを感じましてけれど)
ところでこの作品、時代はいつなのでございましょう?
1980-1990年代的なお歌が出てくる一方、
スマホを持っていたりスカイツリーも出てくるそうでございます。
コンプラ発言もございましたし。
1980-1990年代的なお歌が出てくる一方、
スマホを持っていたりスカイツリーも出てくるそうでございます。
コンプラ発言もございましたし。
でも、アクロバティックさらさらのエピソードは
1991年の暴対法以前を思わせますし、
そうすると1990年代のほうがエピソードの流れとして自然。
1991年の暴対法以前を思わせますし、
そうすると1990年代のほうがエピソードの流れとして自然。
いったいどうなっているのでございましょう
正直、物語は1980-1990年代、風物は現代と、
あえてそのまま受け容れるのがよかろうと思います。
あえてそのまま受け容れるのがよかろうと思います。
歌舞伎やシェイクスピア劇にもそのようなものはございますな。
読者に共感性を持たせるためとか、
キチンと時代を描くことの面倒くささを避けるためかとも思います。
キチンと時代を描くことの面倒くささを避けるためかとも思います。
ですが、この作品のこと。
もしかすると、そこに大きな意味が隠されていたりするのかもしれません。
みんな捨てろ!!
YouTubeを見ておりましたら、
というのがございまして……。
『ネコジャラ市の11人』については、
以前からこのブログで書こう書こうと思っておりましたので、
つい書き込んでしまいました。
以前からこのブログで書こう書こうと思っておりましたので、
つい書き込んでしまいました。
他にもっとコメントするに適したところがある、あったと思うのですが、
タイミングでございますな。
書き込んだのはこんな感じ。
『空中都市008』1969年4月-1970年4月は、
小松左京先生も大きくお関わりになっていた
大阪万博(1970)の宣伝という意味が大きくあったと思われます。
たとえば
エアシューターによる宅配システムが故障して荷物が別の人に届いちゃった、
というエピソードがございましたが、
そのように未来の生活を提示し、
トラブルがあっても前向きに生きていく姿が提示されていたのですね。
小松左京先生も大きくお関わりになっていた
大阪万博(1970)の宣伝という意味が大きくあったと思われます。
たとえば
エアシューターによる宅配システムが故障して荷物が別の人に届いちゃった、
というエピソードがございましたが、
そのように未来の生活を提示し、
トラブルがあっても前向きに生きていく姿が提示されていたのですね。
それに対して次の『ネコジャラ市の11人』は、
主題歌からして「みんな捨てろ!」ですし、
公害問題などがクローズアップされた時代を反映し、
科学や物質文明の負の部分に対する風刺が強めに出ております。
主題歌からして「みんな捨てろ!」ですし、
公害問題などがクローズアップされた時代を反映し、
科学や物質文明の負の部分に対する風刺が強めに出ております。
たとえば
プラスチックならなんでも作れる、と工場を作ったら
機械が止まらなくなってそこらじゅうプラスチックだらけになっちゃった、
どうしよう…みたいな話でございますな。
プラスチックならなんでも作れる、と工場を作ったら
機械が止まらなくなってそこらじゅうプラスチックだらけになっちゃった、
どうしよう…みたいな話でございますな。
ミュージカル仕立てになっていて楽しい作品ではございましたが、
そうしたあたりがNHKの上の人の怒りを買ったのでございましょう。
それで火山爆発とあいなったものと思われます。
あとでも説明いたしますが『ネコジャラ市の11人』は物語中盤で、
ほとんどの登場人物が行方不明となるという
空前絶後のテコ入れを行っているのでございますよ
☆ ☆ ☆
ほとんどの登場人物が行方不明となるという
空前絶後のテコ入れを行っているのでございますよ
☆ ☆ ☆
というわけで、『ネコジャラ市の11人』でございます。
主題歌はこんな感じ。
映像はサイケでシュール、
テーマは「みんな捨てろ」とヒッピー文化、
コーラスの入り方とかセリフの掛けあいは小劇場的。
不気味な余韻を残す終わり方。
(上のNHKアーカイブでは最後が切れておりますゆえ、
気になった方はこちらも……)
テーマは「みんな捨てろ」とヒッピー文化、
コーラスの入り方とかセリフの掛けあいは小劇場的。
不気味な余韻を残す終わり方。
(上のNHKアーカイブでは最後が切れておりますゆえ、
気になった方はこちらも……)
近ごろ、YouTubeでは「1950's Super Panavision 70」という
一連の作品を見ております。
1980年代以降の映像作品が1950年代に作られていたらという想定で、
生成AIを使って作られた映画の予告編でございますな。
一連の作品を見ております。
1980年代以降の映像作品が1950年代に作られていたらという想定で、
生成AIを使って作られた映画の予告編でございますな。
1つのチャンネルではなく、
いくつものグループがこのテーマで作っておりまして、
非常に凝ったものから、キャラクターを並べただけのものまで、玉石混淆。
カテゴリータイトルはこのとおりではないものもございます。
『スター・ウォーズ』『バットマン』『ブレードランナー』
『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『ターミネーター』
『ハリー・ポッター』etc……。
有名どころは大抵餌食にされております。
特に有名な作品には、何種類もの二次作品が存在いたします。
ので、もしも、以下に例に挙げたような画がなかったとしたら、
同じ作品を元とした違うものだと思ってください)
ので、もしも、以下に例に挙げたような画がなかったとしたら、
同じ作品を元とした違うものだと思ってください)
1950年当時の映像技術を再現というわけではございませんで、
1950年代パンクと申しますか、作品自体や現代の感覚を活かしつつ、
パロディ的にそれを'50年代に落とし込んでいくという感じでございまして、
たとえば、『スター・ウォーズ』のメカでございましたら、
あのゴテゴテとした外観は変えずに、
『スタートレック」風のデザインを採り入れたりですね、
R2-D2にキャタピラをつけてみたり……。
船内もメーターとかボタンとかが並び、
レトロフューチャーを醸し出しております。
1950年代パンクと申しますか、作品自体や現代の感覚を活かしつつ、
パロディ的にそれを'50年代に落とし込んでいくという感じでございまして、
たとえば、『スター・ウォーズ』のメカでございましたら、
あのゴテゴテとした外観は変えずに、
『スタートレック」風のデザインを採り入れたりですね、
R2-D2にキャタピラをつけてみたり……。
船内もメーターとかボタンとかが並び、
レトロフューチャーを醸し出しております。
『ブレードランナー』ですと
ポリススピナーが底部にゴチャメカが盛られた
流線型のスーパーカーになっていたり……。
そういうのがやりたいのでございましょうな。
『スターシップ・トゥルーパーズ』もあったので期待して見たのでございますが、
パワードスーツは単なる普通の宇宙服でございました。
アチャラではやっぱりそうなるのかなぁ。
トリの翼のような特殊化した構造に付随する機能や、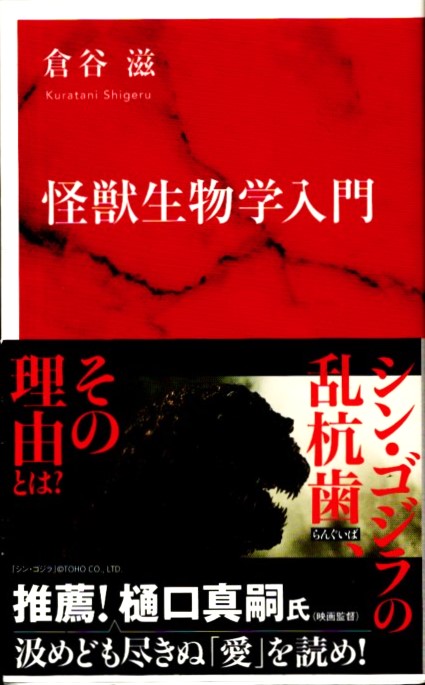
それに基づいた適応的行動パターンは
文字通り「論理(ロジック)」として整合的に語られる。
たとえば「空を飛ぶための翼」のように。
しかしそれは本来「辻褄(つじつま)が合っている」
という以上のことを意味しない。
なのになぜか「飛ぶために翼を持つ」という、
一種の「目的論」としてそれが語られることが多い。
無論、動物の形を決めた「目的」など、
この世にあった試しはない。
「目的」をもって生物を作ったものもいるはずはない。
だからこそ、生物学の世界では目的論的説明はご法度とされる。
むしろ進化生物学的に問題となるのは
「なぜそうなったか」という経緯なのである。
(『怪獣生物学入門』倉谷滋:著
/集英社インターナショナル新書/2019/10)。
文字通り「論理(ロジック)」として整合的に語られる。
たとえば「空を飛ぶための翼」のように。
しかしそれは本来「辻褄(つじつま)が合っている」
という以上のことを意味しない。
なのになぜか「飛ぶために翼を持つ」という、
一種の「目的論」としてそれが語られることが多い。
無論、動物の形を決めた「目的」など、
この世にあった試しはない。
「目的」をもって生物を作ったものもいるはずはない。
だからこそ、生物学の世界では目的論的説明はご法度とされる。
むしろ進化生物学的に問題となるのは
「なぜそうなったか」という経緯なのである。
(『怪獣生物学入門』倉谷滋:著
/集英社インターナショナル新書/2019/10)。
これ普通に見かけるし、やりがちなんですよねぇ。
そうしないと説明がややこしくなるってこともございますし、
単に説明するだけならばそれで充分ってこともございますし。
そうしないと説明がややこしくなるってこともございますし、
単に説明するだけならばそれで充分ってこともございますし。
ですがやはり、鳥が自ら(一世代もしくは数世代)の
空を飛ぼうとする意思によって翼を手に入れたとするのは、
生物学的にはご法度なんですねぇ。
SFならばそういう発想ございますけれど。
蛇足ながら、何ものかの意思で、というのも同様でございます。
それが容れられるのなら、科学は宗教に組み入れられてしまいます。
それが容れられるのなら、科学は宗教に組み入れられてしまいます。
それはさておきましても、意思の力が進化に影響をおよぼすのでしたら、
人間に翼が生えてもおかしくないですよね。
歯が何度も生えかわってもいいと思いますし、
みんなもっと身体能力や知能があってもよろしゅうございましょう。
人間に翼が生えてもおかしくないですよね。
歯が何度も生えかわってもいいと思いますし、
みんなもっと身体能力や知能があってもよろしゅうございましょう。
でも、そうはならないのですな。
あるいは、「ざんねんな生き物」のざんねんな部分というのは、
解消されてなければおかしいと申すものでございます。
解消されてなければおかしいと申すものでございます。
(上に収まりきらなかったのでこちらへ)
きのう『ゴーストバスターズ/アフターライフ』をテレビで見ました。
ミニ・マシュマロマンがワンサカあらわれるあたりから。
かわいらしいキャラクターなのに知らなかったなぁ。
ミニのグッズは見かけたことない。
どうしてだろう。
と思いましたら、
そいつらが仲たがいと申しますか、無邪気ないじめあいをするのですな。
相手を火にあぶったり、ミキサーにかけたり
──残酷なシーンになる手前で止まっているのは
レーティングとかの関係なのでございましょう。
『グレムリン』を思い起こさせました。
さらにクライマックスでは主人公たちの邪魔をしたりもいたします。
これじゃあ人気にならない。グッズなんか作ったとしても売れるはずございません。
「映画秘宝」の年間とほほで
『シン・仮面ライダー』が1位になっていておりましたな。
期待は失望の母である。みんな期待していたのでございましょうなぁ。
『シン・仮面ライダー』が1位になっていておりましたな。
期待は失望の母である。みんな期待していたのでございましょうなぁ。
(いや、大滝詠一さんのこの格言は、
他人に期待しても失望するだけだから自分で作れという意味らしいので、
こういう使い方は間違いらしいですけど)。
まぁ、思い入れが強すぎた分、あれもこれもとりたいことがあって
コンセプトがぶれてしまったのでございましょうな。
コンセプトがぶれてしまったのでございましょうな。
テレビで見るならよかった、というご意見もございましたが、
結局それって、映画として見誤っているということでございますものなぁ。
結局それって、映画として見誤っているということでございますものなぁ。
『コナン』でも『ドラえもん』でも、
劇場版は映画としてスケールアップして作りますのに。
いろいろ都合でNGになった場面もあったみたいでございますが、
結局評価されるのは上映された作品でございますからねぇ。
結局評価されるのは上映された作品でございますからねぇ。
(上へ書ききれなかったのでこちらへ)
『リストマニア
インフォグラフィックスで見る驚きの事実』
インフォグラフィックスで見る驚きの事実』
The Listmanics:著
前田亜里:訳
大場義行:編
(2013/9)
という本を図書館から借りてまいりました。
色々なものをいくつか挙げ、
図や説明を入れて紹介したご本でございます。
図や説明を入れて紹介したご本でございます。
その中に、
「56のテレビや映画に登場したロボットとサイボーグ」
という項目があるのでございますな(p.140-141)。
「56のテレビや映画に登場したロボットとサイボーグ」
という項目があるのでございますな(p.140-141)。
そこには、
『タイタンの戦い』のプーボー、『ナイトライダー』のキット、
『ブレードランナー』のレイチェル、『ロボコップ』、
『オズの魔法使い』のブリキ男、『トランスフォーマー』のオプティマス・プライム、
『アイアンジャイアント』、『2001年宇宙の旅』のHAL9000、
『禁断の惑星』のロビー、『新スタートレック』のデータ、
『ターミネーター』のT-800、『メトロポリス』のマリア、
『スターウォーズ』のR2-D2,C-3POなど、
知っている作品あり存じ上げない作品あり、
これってサイボーグやロボットなの? というものあり……。
『ブレードランナー』のレイチェル、『ロボコップ』、
『オズの魔法使い』のブリキ男、『トランスフォーマー』のオプティマス・プライム、
『アイアンジャイアント』、『2001年宇宙の旅』のHAL9000、
『禁断の惑星』のロビー、『新スタートレック』のデータ、
『ターミネーター』のT-800、『メトロポリス』のマリア、
『スターウォーズ』のR2-D2,C-3POなど、
知っている作品あり存じ上げない作品あり、
これってサイボーグやロボットなの? というものあり……。
ファンタジーも含まれておりますからな、
かなり許容範囲の広いバラエティに富んだリストアップ
と申してよろしゅうございましょう。
かなり許容範囲の広いバラエティに富んだリストアップ
と申してよろしゅうございましょう。
2011年までの作品から選ばれたこんなのが、日本未公開作品も含め
56作品セレクトされているわけでございます。
というわけで、ここで問題。
選ばれた56体(数詞はこれでいいのかなぁ)の中には
日本の作品も3つ挙げられてございます。
なんか少ないけれど3つ。
アチャラの方のチョイスなので仕方がございません。
そのうち1つは『鉄腕アトム』(2009)のアトム、
1つは『ゴジラ対メカゴジラ』(1974)メカゴジラ。
1つは『ゴジラ対メカゴジラ』(1974)メカゴジラ。
ではあと1つは何でしょう?
ヒントを1つ出しますが、その前にまずご自身の解答を頭の中で決定して、
それからご覧になられることをお薦めいたします。
それからご覧になられることをお薦めいたします。
というわけで、ヒント。
ヒント:特撮作品です。
これでだいぶ範囲が狭まったんじゃないかな。
そして多分、この時点で今頭に描いていたものが、
外れていた方が大多数だと存じます。
外れていた方が大多数だと存じます。
正直難問、と申しますより無理問でございますな。
おそらく大部分の方がタイトルを聞いても? 、
正解を聞いても??? でございましょう。
正解を聞いても??? でございましょう。
わたくしもタイトル聞いたことはございましたが、
内容については知らない、と申しますよりも無関心でございました。
内容については知らない、と申しますよりも無関心でございました。
というわけで新作ゴジラの情報まいりましたね。
『ゴジラ-1.0』。ゴジラ生誕70年記念で、令和初のゴジラ。
日本で製作された実写版ゴジラの30作品目だそうでございます。
監督・脚本・VFX:山崎貴さん。
正直あまり知らないけど、
「SPACE BATTLESHIP ヤマト」とか「STAND BY ME ドラえもん」
なんかの人らしいです。
この映画、文化の日に初日を迎えるそうでございますな。
夏休みでもお正月でもない中途半端な日でございますから、
文化の日という日自体に意味があるのではないかと存ずる次第でございます。
夏休みでもお正月でもない中途半端な日でございますから、
文化の日という日自体に意味があるのではないかと存ずる次第でございます。
ご存じのとおり、文化の日は日本国憲法が公布された日。
1946年(昭和21年)のことでございます。
それに絡めてくるのでございましょうかねぇ。
年代について推測できるものは、わたくしには見つけることは出来ませんでした。
看板が左書きなのですよねぇ。
調べてみると、それが一般的になるのは
新聞見出し記事がそうなった1946年~1948年あたりみたい。
新聞見出し記事がそうなった1946年~1948年あたりみたい。
その前から左書きのところもあったようでございますが、
一応のヒントにはなると思います。
それと中ほどで電車みたいなものが飛んできますが、
それが電車であれば戦後すぐじゃないんじゃないかと思ったのでございますよ。
戦争によって、電車そのものや、線路上の電線も破壊されてございますから。
ほら、『銀河鉄道999』の蒸気機関車だって、
松本先生が上京の時乗ったSLの記憶じゃないですか。
石ノ森先生も自伝的作品の中で蒸気機関車をよく描いておりますな。
だから、あそこで転がってきたのが電車だったら終戦直後じゃないのかな
とも思ったのでございますが、よく分かりませんでした。
鉄道が必要だった人は多かったので、
急ピッチで復旧したみたいなのでございますよね。
故障や事故も多かったみたいでございますが。
あの乗り物が飛んできたところがレールだったかも、
あれだけの映像ではよく分かりませんし。
上に電線がないのでございますよね。
後ろのほうには電線がございますが。
ですから、あれがレールだとしたら蒸気機関用か
引き込み線のようなところなのかもしれません。
ですから、あれがレールだとしたら蒸気機関用か
引き込み線のようなところなのかもしれません。
服装がモダンなことや、建物がけっこう建っていることをどう見るか……。
わたくしは最初、戦後すぐを時代として予想していたのでございますが、
もっとあと、『ゴジラ-1.0』というとおり、
本当に最初の『ゴジラ』が上映された昭和29(1954)年の1年前、
昭和28(1953)年の話なのかもしれません。
もっとあと、『ゴジラ-1.0』というとおり、
本当に最初の『ゴジラ』が上映された昭和29(1954)年の1年前、
昭和28(1953)年の話なのかもしれません。
復興が順調に進んでいる日本を絶望のどん底に突き落とすという──。
1作目『ゴジラ』のアナザーサイド(庶民サイドとか)的な作品でございますな。
──そっちかなぁ。
わたくしもボンクラですからな。
わからないのは仕方ございません。
☆ ☆ ☆
とまぁ、それはそれとしてここからはわたくしの妄想にございます。
それはそれとするなら当てる気ないな、戯れ言だな、
そうおっしゃる向きには、正解! と申しておきましょう。
そうおっしゃる向きには、正解! と申しておきましょう。
『シン・仮面ライダー デザインワークス』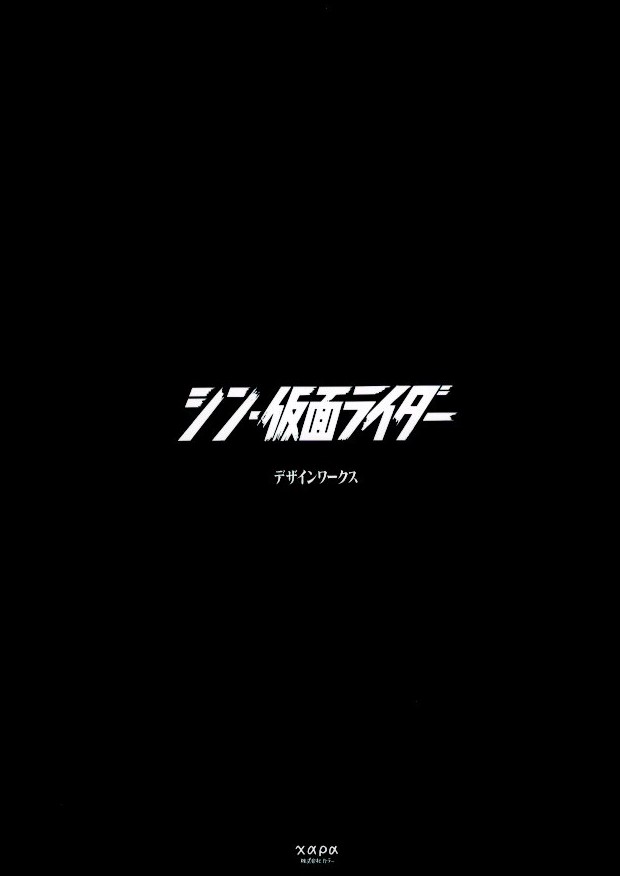
カラー(2023/4)
カラー(2023/4)
パンフレットには一般書店でも販売するようなこと
書いてございましたが、売っていないみたいなので
映画館へ行って買ってまいりました。
首都圏や特別なお店では売っているのかな?
書いてございましたが、売っていないみたいなので
映画館へ行って買ってまいりました。
首都圏や特別なお店では売っているのかな?
『シン・仮面ライダー』を好きな方もそうではない方も、
興味ない方も、買うとよいと思いますよー。
映画とは関係なく、
デザインとして、アイデアとして、企画の変遷として楽しめると思います。
『シン・ウルトラマン』のときもこのようなものあったそうですが、
映画見なかったおかげで存在を知らなかったものなぁ。
その後そういう書物が出ておりませんので、買わなかったことが悔やまれます。
映画見なかったおかげで存在を知らなかったものなぁ。
その後そういう書物が出ておりませんので、買わなかったことが悔やまれます。
やはり興味深いのは企画の変遷でございますな。
サソリは当初原作テレビと同じように男だったそうでございますし、
チョウは女だったそうな。
なんか話がかなり違うものになりそうでございますな。
チョウは女だったそうな。
なんか話がかなり違うものになりそうでございますな。
(上に書ききれなかったのでこちらへ。)
『シン・仮面ライダー』、本郷猛を演ずる池松 壮亮さんは、
1990年7月9日生まれの32歳だそうでございます。
1990年7月9日生まれの32歳だそうでございます。
なんか、仮面ライダーをやるのには、
年齢的に高いのではみたいなことを自分でおっしゃっておりましたが、
城北か城南大学の研究員でございますし、
庵野監督の中ではけっこう妥当な年齢なのだと思います。
ですから、もっと恋愛にふってもよかったのかなぁと思います。
たとえば、セーフハウスのところで、
ルリ子さんが「変なことしないでよ」みたいなこというじゃないですか
(セリフ忘れましたが)。
ルリ子さんが「変なことしないでよ」みたいなこというじゃないですか
(セリフ忘れましたが)。
あそこにこんな場面を入れてもよかったと思うのでございます。
ルリ子「本郷さん」
「裸になって」
「あなたの体をみてみたい……」
(スーツを脱ぎ、上半身裸になる本郷。
そこには、オーグメント化による痛々しい疵痕が無数に走っている)
そこには、オーグメント化による痛々しい疵痕が無数に走っている)
(本郷の体を指で触り、その痕を確かめるルリ子)
ルリ子「これが、父の最高傑作……」
本郷 「……そんな……目で……
見ないで欲しい……」
ルリ子「……ごめんなさい……」
なんて場面を挟めば、本郷がどんな怪物化を遂げたかも描けるし、
それを起点にルリ子との距離も少しだけ近づくと思うのでございますが。
岡本喜八監督の『殺人狂時代』を視ることができたので、
『シン・仮面ライダー』をダシにそれを語っていきたいと存じます。
『シン・仮面ライダー』をダシにそれを語っていきたいと存じます。
どうやって視たかは秘密。
Satsujin kyôjidai だったか The Age of Assassins 、
「日本語で」ではなく「すべてのサイト」で動画検索しますとですねぇ……。
「日本語で」ではなく「すべてのサイト」で動画検索しますとですねぇ……。
……
予告編がございましたので、それを貼っておきましょう。
(どうもYouTubeとニコニコしか貼れないみたい……)
リンクってあまり、貼りたくないのでございますけれどね。
https://youtu.be/JmT1qMEnV9k
※ 予告編からイメージする派手さと本編の面白さは
ずれたところにあると存じますので、それはご承知おきを。
☆ ☆ ☆
ずれたところにあると存じますので、それはご承知おきを。
☆ ☆ ☆
というわけで、『殺人狂時代』
まずは、原作とされている都筑道夫先生の『なめくじに聞いてみろ』と
『殺人狂時代』の関連でございます。
『殺人狂時代』の関連でございます。
岡本喜八監督の『殺人狂時代』見ました~。
こういうのって、気を持たせてなーんだというのはガッカリいたしますので、
先にわたくしの答えを書いておきますと、
死神グループとの関係はほぼ無いともうしてよろしゅうございましょう。
先にわたくしの答えを書いておきますと、
死神グループとの関係はほぼ無いともうしてよろしゅうございましょう。
ただし『殺人狂時代』、視る価値は十分ある作品だと存じます。
というわけで、近ごろは結論だけでいいという方も多いみたいなので、
そういう方はここまででございますね。
そういう方はここまででございますね。
いやぁ、親切だなぁ。
さてまぁ、
今回は前回のおさらいにございます。
詳しくは前回の記事を読んで、でよろしいのでございますが、
そう言ってもどうせ読まないでございましょうからここに書いておきます。
そう言ってもどうせ読まないでございましょうからここに書いておきます。
あれから付け加わったこともあるでしょうし──。
というわけでまず、
ショッカーの死神グループは
深い絶望を帯びた人間が幹部に選ばれるって話でございますよね。
それ聞いて、そんな幹部の絶望を映画ではどう表現するのか、
と思ったのでございます。
と思ったのでございます。
もしかするとやたらと深刻な怪人ばかりが出てくる話?
そう思って映画を見に行ったのでございますね。
そう思って映画を見に行ったのでございますね。
でも、そんなことない。
見た方は賛同いただけると思うのですが、むしろ怪人たち、
みんななんか楽しげでございましょ?
みんななんか楽しげでございましょ?
こりゃまた、どういうわけだ!?
でございますよ。
で、考えたのが、
この方々の抱いているのは、絶望ではないのではないか、だとすれば何か、
ということなのでございます。
この方々の抱いているのは、絶望ではないのではないか、だとすれば何か、
ということなのでございます。
なぞのまとめ 1月~2月の中から、
ガメラを始めとするトクサツ映画関連だけ抜き出しておくことにいたします。
2023/01/03 「鯨神」を見る。GyaOで。
伊福部昭先生の土俗的で迫力ある音楽が作品に合っている。
活劇・特撮部分は冒頭と終盤の十数分ぐらいで、個人的にはそこだけ面白い。
物語としては鯨神と呼ばれる巨大な鯨を殺すことに執念を燃やす村の話で、
村長が鯨神を殺したものには自分の一人娘と家(つまり村長の地位だ)をやろう
というのだから古典的だ。
その中で人間関係や神としての鯨との関係性が描かれているのだが──。
なにか手塚先生とか石ノ森先生のマンガでも
そんな話を見たことがあるような気がする。
芥川賞を取ったという宇能鴻一郎先生の原作はどうだったのだろう。
中編ぐらいみたいなので展開としてはさほど変わらないだろうが、
情念みたいなものを描くのは小説の方が得意そうだ。
ガメラを始めとするトクサツ映画関連だけ抜き出しておくことにいたします。
2023/01/03 「鯨神」を見る。GyaOで。
伊福部昭先生の土俗的で迫力ある音楽が作品に合っている。
活劇・特撮部分は冒頭と終盤の十数分ぐらいで、個人的にはそこだけ面白い。
物語としては鯨神と呼ばれる巨大な鯨を殺すことに執念を燃やす村の話で、
村長が鯨神を殺したものには自分の一人娘と家(つまり村長の地位だ)をやろう
というのだから古典的だ。
その中で人間関係や神としての鯨との関係性が描かれているのだが──。
なにか手塚先生とか石ノ森先生のマンガでも
そんな話を見たことがあるような気がする。
芥川賞を取ったという宇能鴻一郎先生の原作はどうだったのだろう。
中編ぐらいみたいなので展開としてはさほど変わらないだろうが、
情念みたいなものを描くのは小説の方が得意そうだ。
2023/01/04 「大怪獣ガメラ」を見る。高エネルギーを求めるガメラを
コンビナートにとどめておくため、
石油タンク車をそこに向かって走らせる場面があるが、もしかすると
「シン・ゴジラ」のヤシオリ作戦はこのイメージもあるのではと思えた。
(のですが、後で考えると、ゴジラにもそんなシーンがあったような……)
人類の手に負えないような怪獣を最終的にどうするかは苦労するところだ。
ゴジラは海に帰したが……。
この作品の方法は後に「ウルトラマン」のある話でパロディ的に使われる。
それはさておき、ちょっとご都合。
Z計画があったのはいい。
でもあれ、そうした計画があったとしても、
ガメラのためにいろいろと準備しなけりゃ出来ないでしょう。
それに……。
むかしテレビで見たときも、ここちゃちに感じたような気がします。
コンビナートにとどめておくため、
石油タンク車をそこに向かって走らせる場面があるが、もしかすると
「シン・ゴジラ」のヤシオリ作戦はこのイメージもあるのではと思えた。
(のですが、後で考えると、ゴジラにもそんなシーンがあったような……)
人類の手に負えないような怪獣を最終的にどうするかは苦労するところだ。
ゴジラは海に帰したが……。
この作品の方法は後に「ウルトラマン」のある話でパロディ的に使われる。
それはさておき、ちょっとご都合。
Z計画があったのはいい。
でもあれ、そうした計画があったとしても、
ガメラのためにいろいろと準備しなけりゃ出来ないでしょう。
それに……。
むかしテレビで見たときも、ここちゃちに感じたような気がします。
『特撮の地球科学 古生物学者のスーパー科学考察』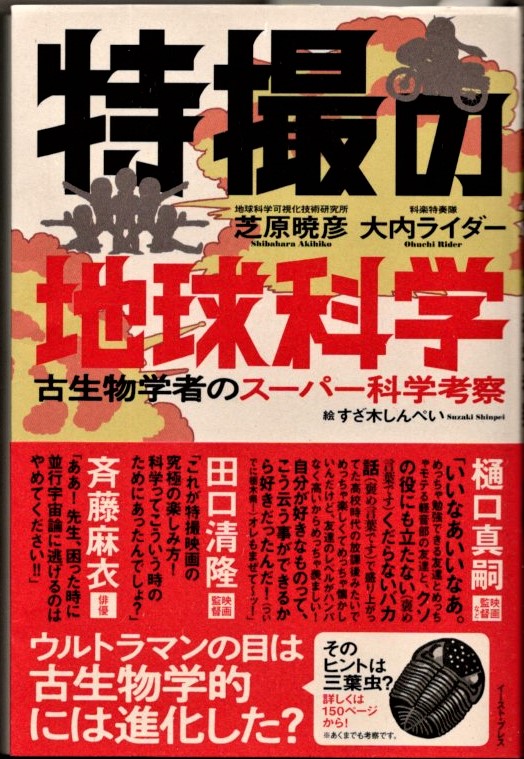
芝原暁彦・大内ライダー:著
(イーストプレス/2021/4)
『シン・ウルトラマン』公開の
少し前に買った本にございます。
映画にあわせて目立つところに置かれていたのでしょうが、
それにみごとに釣られて買ってしまいました~。
最新刊だと思ったら、出たのはその1年ほど前で、
書かれたというか対談が行われたのは
『シン・ウルトラマン』の
最初のポスターが公開されたころのようです。
少し前に買った本にございます。
映画にあわせて目立つところに置かれていたのでしょうが、
それにみごとに釣られて買ってしまいました~。
最新刊だと思ったら、出たのはその1年ほど前で、
書かれたというか対談が行われたのは
『シン・ウルトラマン』の
最初のポスターが公開されたころのようです。
特撮オタクで古生物学者の芝原暁彦先生のお話を
やはり特撮オタクの大内ライダーさんが聞き役となって
回していくという、対談とインタビューの中間的な対談でございます。
やはり特撮オタクの大内ライダーさんが聞き役となって
回していくという、対談とインタビューの中間的な対談でございます。
特撮を考察するにあたって、本書では2つの条件をつけております。
① 特撮作品の画面に映っていることはすべて「事実」と捉える。
② 特撮作品が作られた時代の技術的背景や世相も考慮する。
要するに、科学で空想を否定する『空想科学読本』のような本ではない
ということでございますな。
ということでございますな。
(前回からの続き)
とは申せ、『シン・キャプテンウルトラ』をやってくれるとは限りません。
ウルトラシリーズ第3弾は跳ばして、
第4弾をやる可能性だって、あるかも、大いにあるかもです。
その場合、『シン・ウルトラセブン』をやる場合の、
最初の10分はいかなものとなりましょう。
最初の10分はいかなものとなりましょう。
考えてみることにいたします。
『シン・ウルトラマン』と同様、最初は前作のダイジェストから始まると存じます。
ですから。アナウンスされております『シン・仮面ライダー』に続く『シン~』は何だろう、
何がいいと、下馬先でヤジさんたちがいろいろおっしゃっておられます。
何がいいと、下馬先でヤジさんたちがいろいろおっしゃっておられます。
やれ『シン・ガンダム』だの『シン・ウルトラセブン』だの
『~ヤマト』だの『~豪ワールド』だの『~ナウシカ』だの……。
『~ヤマト』だの『~豪ワールド』だの『~ナウシカ』だの……。
これらの根拠は、
もちろんおっしゃっている方が見てみたいというのが大きくございましょうが、
庵野監督が好きだった、もしくは作りたかったと表明している
ことも理由でございますよね。
もちろんおっしゃっている方が見てみたいというのが大きくございましょうが、
庵野監督が好きだった、もしくは作りたかったと表明している
ことも理由でございますよね。
しかし、それでよろしいのでございましょうか?
そのような作品のやりたいことって、
もう『エヴァンゲリオン』など、自分の作品でやっちゃっておりますよね。
絵的なことからテーマ的なものまで含めて。
もう『エヴァンゲリオン』など、自分の作品でやっちゃっておりますよね。
絵的なことからテーマ的なものまで含めて。
ですから、好きな作品を好きなように作っていけば行くほど、
先細りになっていくと思うのでござます。
そのうち、意外に早く、
マンネリだという声が聞こえるようになるのではござ今せんでしょうか。
マンネリだという声が聞こえるようになるのではござ今せんでしょうか。
『シン・ウルトラマン』でさえ、それが見えてしまう。
庵野監督の本当のファンはそれで良いといたしましても、
ネタ元の作品のファンは、庵野先生のテーマは要らない。
絵的な美しさと、物語の楽しさ、濃さを最先端のものにして、
内容については元作品を損なわないように忠実に忠実に作りあげて欲しい、
という思いがあるのではございませんでしょうか。
ネタ元の作品のファンは、庵野先生のテーマは要らない。
絵的な美しさと、物語の楽しさ、濃さを最先端のものにして、
内容については元作品を損なわないように忠実に忠実に作りあげて欲しい、
という思いがあるのではございませんでしょうか。
ただ一方、例は挙げませんが、作家性がない人がリメイクをしても、
結局凡作、元以下どころか見る価値無しにしてしまう可能性だってございますよね。
──まぁ、個性があってダメという場合もございますが、
それは話にならないとしてでございます。
それは話にならないとしてでございます。
ちょっと脇にそれてしまいましたね。
要するに、いつも同じと言われないためには、ガス抜きが必要。
テーマ性などまったくない、ただ面白いだけの作品を
ここでやるべきだと思うのでございます。
ここでやるべきだと思うのでございます。
というわけで。ですね。
何がいいだろうと考えていたところ、ほころびからころり転がり落ちてまいりました。
そう、題にもあげた『キャプテンウルトラ』でございます。
ウルトラシリーズ第3弾。
しかも主人公、キャプテン・ウルトラの本名は本郷武彦ですよ。
まず一切を無視したとしても、
『シン・ウルトラマン』『シン・仮面ライダー』の次にやる作品として
これほどふさわしいものはございません。
これほどふさわしいものはございません。
さらにこの作品、深いテーマ性などというものはございません。
時代劇よろしく、悪い宇宙人をバッタバッタとなぎ倒していく話でございます。
時代劇よろしく、悪い宇宙人をバッタバッタとなぎ倒していく話でございます。
最終回なんて、虚空に∞のマークを描いて、宇宙は無限だ、でございますよ。
明るい未来志向そのものでございます。
庵野監督も深い思想性など入れることなく、
ただ面白さだけを追求できることでございましょう。
ただ面白さだけを追求できることでございましょう。
……まぁ、深いものを入れようと思えばいくらでも入れられるとは存じますが。
とにかくですねぇ。
『キャプテンウルトラ』というのは、
『キャプテンフューチャー』+東映ヒーローもの+トクサツでございますから、
使い勝手がいいのでございますよ。
『キャプテンフューチャー』+東映ヒーローもの+トクサツでございますから、
使い勝手がいいのでございますよ。
『スタートレック』だって『サンダーバード』だって何だってできる。
怪獣や宇宙人を登場させてもいいですし、アクションだって十分出来る。
SFにもファンタジーにもホラーにも振ることができる。
怪獣や宇宙人を登場させてもいいですし、アクションだって十分出来る。
SFにもファンタジーにもホラーにも振ることができる。
『ナウシカ』だってスタートレックの映画みたいな感じてできましょう!!
それに『キャプテンウルトラ』に強いこだわりを持っている人って
そんなにいるとも思えません。
大々的に改変しても文句は言われません。
むしろ喜んでくれるでしょう。
宇宙ステーションや怪獣星人も自由に改変していいでしょうし、
シュピーゲル号の合体や発射シークエンスをもっと凝ったものにしてもいい。
シュピーゲル号の合体や発射シークエンスをもっと凝ったものにしてもいい。
庵野監督にとってもいろいろと楽しめる部分だと思うのでございます。
さらに化ける可能性もございます。
ジョージ・ルーカス監督は『フラッシュ・ゴードン』を撮りたかったのだけど、
権利的に出来なくて『スター・ウォーズ』を作ったというエピソード、
ございましょ?
権利的に出来なくて『スター・ウォーズ』を作ったというエピソード、
ございましょ?
あれでございます。
『キャプテンウルトラ』も『フラッシュ・ゴードン』のようなものでございますから、
それを今の技術、庵野監督の知識と経験で再構築していけば、
『スター・ウォーズ』を越える娯楽作品ができるかもしれないということでございます。
『キャプテンウルトラ』も『フラッシュ・ゴードン』のようなものでございますから、
それを今の技術、庵野監督の知識と経験で再構築していけば、
『スター・ウォーズ』を越える娯楽作品ができるかもしれないということでございます。
というわけで、題にも書いた結論。
庵野監督は『シン・キャプテンウルトラ』を撮るべきだ!!
とあいなるのでございます。
とあいなるのでございます。
カレンダー
プロフィール
HN:
道化の真実
性別:
男性
趣味:
ゲームブック
最新記事
(04/20)
(04/14)
(04/13)
(04/06)
(04/05)
最古記事
リンク
最新CM
[04/05 道化の真実]
[04/03 ポール・ブリッツ]
[03/07 道化の真実]
[03/03 ポール・ブリッツ]
[01/12 道化の真実]
最新TB
カテゴリー
ブログ内検索
P R
フリーエリア
<

